千利休というと「わび茶」を完成した人物として有名ですが、文化人であるにも関わらず武士のように切腹で最期を遂げています。
茶聖とまで呼ばれた千利休がなぜ切腹しなければならなかったのか?
今回は漫画「へうげもの」にも登場する千利休について詳しく解説していきます。
| 千利休 |
|---|
 |
| 【出身国】和泉国 堺 |
| 【生没年】1522年~1591年 |
【千利休を知る5つのポイント】
- 茶道千家流の始祖であり〝茶聖〟と呼ばれた
- 信長を恐れ、秀吉を軽んじていた?
- 大阪城内では豊臣秀長(秀吉の弟)と同等の権威を持っていた
- 秀吉に切腹を申し付けられて自害
千利休と言えばお茶。
お茶と言えば千利休というくらい日本では名の知れた茶人です。
信長・秀吉という二人の天下人に仕え、政治にまで影響を及ぼした茶人は日本中探してもこの人くらいのものです。
そして、皆さんのよく知る〝千利休〟という名前ですが、実は晩年の名前なんです。
彼は本命を〝田中与四郎〟といい、法名を〝宗易〟もしくは〝抛筌斎(ほうせんさい)〟と号しています。
法名とは仏弟子となった人の二つ名のようなものと考えてください。
利休、という名前は宮中参内の際に町人の身分ではいけないと、天親町天皇から授かった居士号なのです。
利休は茶人としての人生のほとんどを〝宗易〟と名乗っていましたが、今回はあえて広く知られた〝利休〟の呼び名を使って彼の生涯をのぞいてみたいと思います。
茶道千家流の始祖であり〝茶聖〟と呼ばれた
茶道の話をしていると、よく裏千家、表千家、なんて耳にしますよね。
これらは利休の孫である千宗旦の子供達が作ったもので、利休はその始祖であり、茶聖として文字通り崇め奉られていたわけです。
かくいう利休も、初めから茶の道を究めていたわけではありません。
父親である田中与兵衛は立派な商人で、利休はそんな父の跡を継ぐために知識教養、品格を身に付けようと茶道を始めました。
そこで彼は、のちの師となる武野紹鴎と出会い、みごと茶の道にどっぷりつかってしまいます。
「欠けているからこそ美しい、侘びの形こそが、人間の本髄――茶の道とは奥が深い」と利休は実家を継ぐことを辞め、茶の道に専念することになります。
信長を恐れ、秀吉を軽んじた
織田信長は町との繋がりを強めるために、茶人として既にかなり名を広めていた利休を茶頭として重用します。
もちろん道楽のためではありません。
茶の湯は亭主と客が一対一で狭い室内で対峙します。
そのため、心の乱れがあれば挙動が不自になり、相手にもすぐに伝わります。
つまり、茶の湯というのは武士の精神統一の方法としても、密談の方法としても丁度良かった訳です。
また、茶の湯を開くことがきるのを限られた人間だけにしたことで、彼らは「御茶湯御政道」を許されたと名誉に感じたといいます。
元手もいらず家臣たちの忠誠心を煽ることができる――。
信長にとっては茶道も政策の道具でした。
信長が本能寺にて討死したあとは、利休は秀吉のお茶頭となります。
しかし利休は信長よりも秀吉のことを軽視していました。
なぜかというと、茶の湯を政策の一環として考えていた信長に比べ、秀吉は純粋に茶道を楽しみ、その作法の奥ふかい広がりを味わっていたからです。
茶人であれば茶の道の奥深さに共感してくれる主君のほうがいい気もしますが、どうやら利休はそう思わなかったようです。
茶を通して世のことわりをとく利休に対し、その真髄に触れながらもいかにして茶の湯を自分の利に繋げるか、獲物を狙う猛獣のように油断ならない主君であった信長は、畏れる対象でありながら仕えるにふさわしい相手として利休の中にありました。
秀吉の側近として仕えることに慣れてきた利休は、彼が信長よりずいぶんと分かりやすい人間だと、ものたりなさを感じたのかもしれません。
秀吉が利休を警戒した理由
茶人として有名な千利休ですが、利休は単なる文化人ではありません。
そのためには、茶道というものがこの時代にあってどのような役割を果たしてきたのかということを考える必要があります。
千利休は茶室を書院造りの建物から離して草庵というものを創り出しました。
そこは人と人とが話をしながら茶をたしなむ場所。
時には密談の場としても使われています。
つまり諸国の大名や権力者がつながりをもつ場であり、その中心に千利休はいたことになります。
そして名だたる大名や武将が千利休に弟子入りしているのです。
豊臣秀吉に最も恐れられたという蒲生氏郷を筆頭に、豊臣秀吉の宿敵だった明智光秀の娘・ガラシャを妻に持つ細川忠興、他にも前田利家や織田有楽斎など顔ぶれは多彩です。
当然、諸国の情勢や情報は千利休に集まり一大ネットワークができあがります。
現代のように簡単に情報が手に入る時代ではありません。
豊臣秀吉自身も情報の重要性を見抜き、情報に敏感であったからこそ成り上がってきたという経緯もあります。
だからこそ天下を統一した豊臣秀吉にとって、千利休の存在は他の誰よりも驚異に映ったのかもしれません。
織田信長すら達成できなかった天下統一を成し得た豊臣秀吉は、この辺りから歯車が狂い始めてきます。
嫡男である鶴松を病気で亡くし、朝鮮出兵を決行。
豊臣秀頼が誕生すると甥の豊臣秀次を自害に追い込むなど傍若無人な行動が目立ち始めます。
自分の相談役にまでした千利休に切腹を命じたのもこの時期です。
あれだけ人とのつながりを大切にし、「人たらし」とまで呼ばれた豊臣秀吉が、天下統一後は人が変わったように残忍になっていくことに家臣達は驚きます。
大阪城内で豊臣秀長(秀吉の弟)と同等の権威を持っていた
秀吉は大名たちとの謁見の際、積極的に茶の湯を利用します。
諸大名たちはこの秀吉の茶会の価値を「日本のつきあいに遅れ、恥をかけば、あたらしい支配体制の社会秩序に遅れる」と表現しているほどです。
これほどまでに政治と茶道は深く繋がりを持ってしまったのです。
そして、そこには必ず利休も同席していました。
この頃には利休も秀吉政権の機密を知り尽くしており、戦場に置いての書状や外交など重要な役目をいくつも担っていました。
当時の利休の権勢がどれほどであったか物語る逸話があります。
豊後の大友宗麟が大阪城に到着して秀吉に謁見した時、付き添いの秀長(秀吉の弟)が彼の手を取って以下のように言いました。
「何事も何事も、私がそばにいるのでご安心ください。内々の儀は宗易が、公儀のことは宰相が存じています。あなたのためにならないことは致しません、ご安心ください」
これはつまり大阪城内で内々のことは利休が、公のことは秀長が全てを取り仕切っている、すなわち権力の頂点に立っているということになります。
こうなると利休はもはやただの茶人ではありません。
彼の名はこうして各国に広まっていきました。
秀吉を怒らせ切腹を申し付けられる
利休の死に際と言えば、秀吉に申し付けられての切腹ということは分かっていますが、その理由は未だにはっきりとはしていません。
茶道に関する考え方で対立したとも、石田三成の怨恨をうけたためともいわれています。
どちらにしても、権力を持ちすぎた利休を秀吉が危険視したことは間違いありません。
この時の利休はそれほど影響力を持っていたのです。
例えば千利休が徳川家康と手を結んで豊臣政権を脅かすことになった場合、千利休の息のかかった大名たちがこぞって徳川家康側につくかもしれないのです。
1度権力を手にした者はそれを失う事を必要以上に恐れると言います。
あれだけ人材を生かして勢力をつけた豊臣秀吉でも、その天下を守るために威勢を万民に示し、逆らうものはすべて滅ぼすという発想に転換していったとしてもおかしくはありません。
一般的に豊臣秀吉が激怒した理由は、大徳寺の門の改修時に千利休の雪草履姿の木造を楼門の上に設置し、その下を豊臣秀吉に通らせたからというものが有力です。
その他の原因としては
- 利休の一声で茶器が高額になる影響力がおもしろくなかった。
- 秀吉と茶道に対する考え方で対立した。
- 政治の事に口出しをするようになり影響力もでてきたため。
- 莫大な財を成していたから。
といったものがあります。
基本的には増長した千利休の慢心を懲らしめるための切腹というのが定説です。
ハッキリとした原因は今も謎のままですが、千利休は弁明をせずに死を受け入れたといいます。
その時に残した有名な辞世の句があります。
「利休めは とかく冥加のものぞかし 菅丞相になるとぞ思へば」
現代語に訳すと、「私、利休はまことに幸せ者である。菅原道真のように怨霊になって秀吉に復讐でき、人々に尊敬されるのだから」となります。
死を間近にした際に詠んだ句に茶の一言も入っていないことから、利休の中にある秀吉への恨みの深さが見て取れます。
かくして、切腹を迫られた利休は命乞いをすることもなく、武士のように潔く腹を切ったのでした。
その行為自体は明らかに豊臣秀吉に対して示した千利休の男としての意地であり、プライドであり、そしてまた強い諫言の意味を含んでいたのではないかと思います。
一大ネットワークがあるが故に豊臣秀吉に用いられ、あまりにも政治にかかわり過ぎたことが千利休の首を絞める結果になったことは皮肉な結果です。
千利休が切腹して果てたすぐ後に、豊臣秀吉は嫡男を病気で失い、やがて狂ったような統治を施していくことになります。
そしてその時には傍には豊臣秀吉に諫言できるものはおらず、人心は徳川家康へと移っていくことになるのです。
【関連記事】
【参考資料】
- 戦国業師列伝(津本陽)
- 辞世の言葉で知る日本史人物事典(西沢正史)
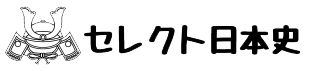






彼は本命を〝田中与四郎〟→本名だと思います
豊後の大友宗麟が大阪城に到着して→大阪城よりも大坂城が適当かと
これはつまり大阪城内で内々のことは利休が→大阪城よりも大坂城が適当かと